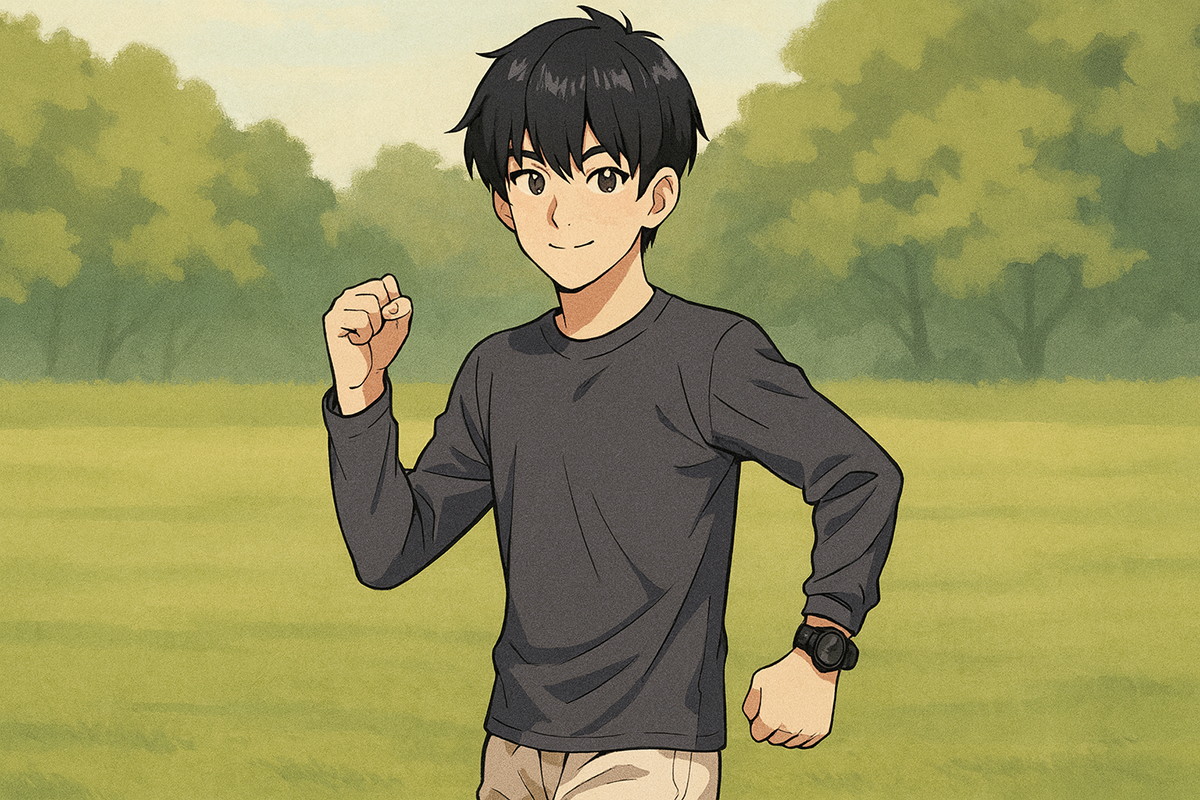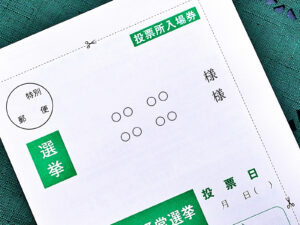最近「スマホ新法」という言葉をよく耳にします。
2024年6月に成立したスマホ新法は、正式には「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」。
この法律は2025年12月18日までに施行される予定で、AppleとGoogleという大手IT企業が対象となり、今後スマートフォンのアプリストアや決済システムに大きな変化をもたらすことになります。
スマホ新法が施行された場合のメリットとデメリットを分かりやすく整理し、今後どうなるのか解説します。
スマホ新法ってなに?

スマホ新法はOSやアプリストアやブラウザや検索などの特定ソフトウェアで公平な競争を促し、Apple・Google以外のアプリストア利用や別の課金方法をユーザーが選択できるようになります。
法律の対象はスマートフォンで利用される特定ソフトウェアに限定され、指定事業者(※)が開発者や利用者の選択を不当に妨げる行為を禁止する枠組みです。
指定事業者とは、Apple Inc.とiTunes株式会社(共同でアプリストアを運営)、Google LLCの3社を指します
3社が独占していたOS(基本ソフト)・アプリの入手方法・課金方法・ブラウザ選択に新しい選択肢が加わるということになります。
スマホ新法のメリット
スマホ新法が施行されると、第三者アプリストアや代替決済・新しいブラウザや検索方法が認められる方向となり、指定事業者が自社決済や独自環境をユーザーに強制することができなくなります。
- アプリ購入ストアや決済方法の選択肢が増え、指定事業者に支払われていた手数料(15~30%)が不要になった分の価格改善が期待できる
- アプリなどの開発者にとって販売経路と課金手段の自由度が広がる
- 利用者にとってはスマホに関わるサービス選択の幅が広がる
価格が下がるというのはもちろん大きなメリットです。
サブスクリプション型のサービスも多いので、毎月安定して多額の課金をしている人も多いですよね。
スマホ新法のデメリット
価格などの改善が見込まれる一方で、セキュリティや品質が低下する恐れがあります。
スマホに関する様々な選択肢は広がりますが、配布元の信頼性や安全性の確認、その企業やアプリがその後も存続できるかどうかの見極めも重要になります。
いままで完成度と安全性があたりまえに確保されていたものが、AppleやGoogleを通さないアプリやサービスにはありません。
AppleやGoogleはもうユーザーを守る義務が無くなり、トラブルはすべてユーザーの自己責任になるのです。
なんかちょっと怖いですね。
通信料金と端末購入はどうなる?

スマホ新法はソフトウェア競争に関する法律であり、通信料金や端末の値引き規制を直接定めるものではありません。
法律の対象はOSやアプリストアやブラウザや検索などの特定ソフトウェアで、料金プランや端末販売制度は別の制度で扱われます。
スマホ新法が施行されても通信料金や端末購入にはあまり影響が無く、まずはアプリや課金やブラウザとウェブ検索が大きく変わっていくと予想されています。
無料通話アプリなどによって通話料金が現状より下がる可能性もあります。
スマホ新法はいつから適用?生活はどう変わる?
スマホ新法は公正取引委員会が法令とガイドラインを公表して周知と執行体制の準備を進めており、2025年12月18日に全面施行の予定です。
年内から来年にかけて対応アプリや新しい課金選択やブラウザの変化が段階的に見え始め、2025年12月以降は本格的な選択肢拡大が予想されています。
実装状況はアプリやプラットフォームごとに差が出る可能性がありますが、アプリ配布元やレビューの確認、二段階認証やOS更新の徹底で安全性を高めていく必要がありそうですね。